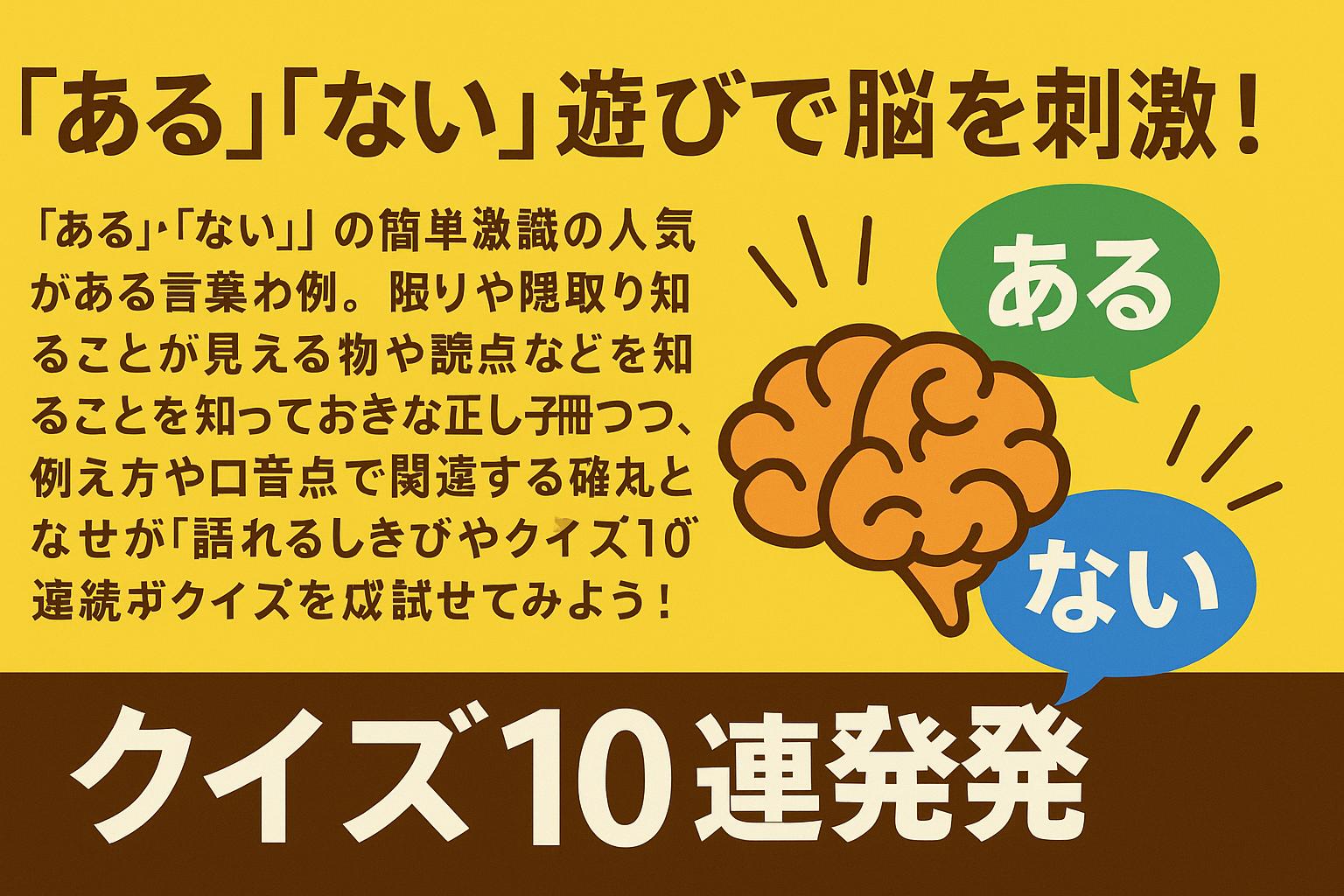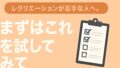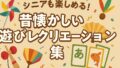はじめに
ちょっとしたスキマ時間に、楽しく頭を動かせるアクティビティを探している方におすすめなのが、「ある」「ない」遊びです。
この遊びは、一見シンプルながらも、観察力や発想力、柔軟な思考が試される奥深いゲームです。
「ある」と「ない」の違いを見つけるというルールですが、そこにはちょっとした“ひっかけ”や“気づき”が隠されていて、ひらめいたときのスッキリ感は格別。
子どもから大人まで、幅広い年代で楽しめるのも魅力のひとつです。
今回ご紹介するのは、「ある」「ない」遊びの基本ルールと、すぐに使える楽しいクイズ10問です。
友達同士や家族、学校の授業、レクリエーションなど、さまざまなシーンで活用できます。
さらに、問題を自作すればオリジナルの遊びとして発展させることも可能。
ちょっとした時間で、ひらめき力や言葉のセンスを育てられる「ある」「ない」遊びを、ぜひ取り入れてみてください。
「ある」「ない」遊びとは?
ある共通の法則にしたがって、「あるもの」と「ないもの」に分類される、ユニークで頭を使う言葉遊びです。
参加者は提示された2つの言葉の違いを観察し、その背後にある隠されたルールを見つけ出すという、推理ゲームのような楽しさを味わえます。
たとえば、「りんごには“ある”、みかんには“ない”」といった問いかけからスタートし、「じゃあバナナにはある?なし?」といった具合に発展していきます。
この遊びの面白いところは、明確な答えがあるにもかかわらず、気づくまではまったく予想がつかない点。
文字の中身、発音、意味、形、使われる場面など、あらゆる視点から柔軟に考える必要があります。
法則が見抜けた瞬間には「あっ!」と声が出るほどのスッキリ感が得られ、まさにひらめき力を刺激する知的レクリエーションといえるでしょう。
子どもから大人まで、誰でも簡単に参加できるのに奥深く、繰り返し楽しめるのがこの遊びの魅力です。
ルールの一例
- 単語の中に使われている特定の文字に注目してみましょう(例:「ん」が含まれているかどうか)
- 単語を漢字に変換し、画数の多さや偶数・奇数の特徴に注目する(例:「画数が偶数」や「一画目が縦線から始まる」など)
- 音の数や語感、アクセントやリズムなど、音に関する特徴に注目する(例:「3文字」「濁音が含まれる」など)
- ひらがな・カタカナ・漢字といった表記の種類に注目する(例:「カタカナだけで書ける単語」)
- 形や用途、動作に関連する意味的な共通点にも注目する(例:「動きがあるもの」「手で持って使う道具」など)
このように、出題者だけが法則を知っていて、参加者は出された例と言葉のヒントからその法則を推理していきます。
「なぜあるのか?」「なぜないのか?」という視点を持って、頭をやわらかくしながらじっくり考えていくことで、気づいた瞬間のスッキリ感とともに、観察力や発想力がどんどん磨かれていきます。
慣れてきたら、自分でルールを考えてオリジナル問題を作ってみるのもおすすめです。
「ある」「ない」クイズ10連発(解説付き)
Q1.「さくらんぼ」にはある。「いちご」にはない。何がある?
ヒント:最後の文字に注目!「ぼ」という文字の存在に気づけるかな?意外と盲点です。
解説:「さくらんぼ」には濁音の「ぼ」が含まれています。「いちご」はすべて清音で構成されており、ここが大きな違いです。
Q2.「テレビ」にはある。「ラジオ」にはない。何がある?
ヒント:形状をイメージしてみましょう。画面という“面”があることが答えのカギかもしれません。
解説:テレビには「映像を映す画面」があります。一方、ラジオは音声のみ。視覚情報の有無がポイントです。
Q3.「犬」にはある。「猫」にはない。何がある?
ヒント:「ん」の有無に注目!文字として「ん」が含まれていることに注目しましょう。
解説:「犬」は「いぬ」と書きますが、文字「ん」は入っていません。ただし、別の法則を探る視点が必要。たとえば、「干支にある」「しっぽをよく振る」など別の切り口もあります。
Q4.「カレー」にはある。「シチュー」にはない。何がある?
ヒント:料理をするときの手順を思い浮かべて。炒める工程があるかどうかがポイント!
解説:カレーは野菜や肉を「炒める」ことが多いですが、シチューは煮込みメイン。調理方法の違いがポイントです。
Q5.「時計」にはある。「カレンダー」にはない。何がある?
ヒント:時間と日付、どちらの話?「音を出す」機能がヒントかも?
解説:時計はアラーム音など「音を出す機能」がありますが、カレンダーは視覚的な表示だけ。五感の違いに注目。
Q6.「あさがお」にはある。「ひまわり」にはない。何がある?
ヒント:名前の中の音や文字に注目!ひらがなで見るとわかるかも。「が」がある?
解説:「あさがお」には「が」が含まれます。「ひまわり」には濁音がなく、音の違いがポイントです。
Q7.「学校」にはある。「会社」にはない。何がある?
ヒント:「こども」と関係があるかも?行事や授業のような教育要素がカギです。
解説:学校には「授業」「運動会」などの行事がありますが、会社には一般的にありません。機能や目的の違いに注目。
Q8.「雲」にはある。「雨」にはない。何がある?
ヒント:漢字の部首をよく見て!「雨かんむり」が付いているかどうかがポイントです。
解説:「雲」は「雨かんむり」が含まれている漢字ですが、「雨」は部首ではなく漢字そのもの。構造の違いがヒントです。
Q9.「たけのこ」にはある。「しいたけ」にはない。何がある?
ヒント:「の」があるかないか?助詞の「の」が挟まれているのがヒント。
解説:「たけのこ」には「の」が挟まれていますが、「しいたけ」はひと続き。文構造や言葉のつながりがポイントです。
Q10.「はさみ」にはある。「カッター」にはない。何がある?
ヒント:動かし方や使い方を想像してみましょう。「左右に開閉する」動作があるものです。
解説:「はさみ」は左右に開いて切る動作ですが、「カッター」は一方向のスライド。使用動作に注目すると答えが見えてきます。
おわりに
「ある」「ない」遊びは、見た目以上に奥が深く、ちょっとしたスキマ時間にもぴったりな、誰でも気軽に取り組める魅力的な言葉遊びです。
シンプルなルールながら、観察力や発想力、柔軟な思考力をフル活用する必要があり、大人も子どももつい夢中になってしまいます。
法則に気づくまでのワクワク感、答えがわかった瞬間のスッキリ感がクセになると、多くの人に支持されているのも納得です。
慣れてきたら、自分なりに新しい法則を考えて、オリジナル問題を出題してみるのもおすすめです。
家族や友達と一緒に出し合ったり、学校や高齢者施設でのレクリエーションに取り入れたりと、アイデア次第で使い方は無限大。
頭の体操としても優秀なので、気軽にできて脳の刺激にもなる一石二鳥の遊びです。
ぜひさまざまなシーンで「ある」「ない」遊びを楽しんで、遊びながら“ひらめき力”をどんどん育てていきましょう!